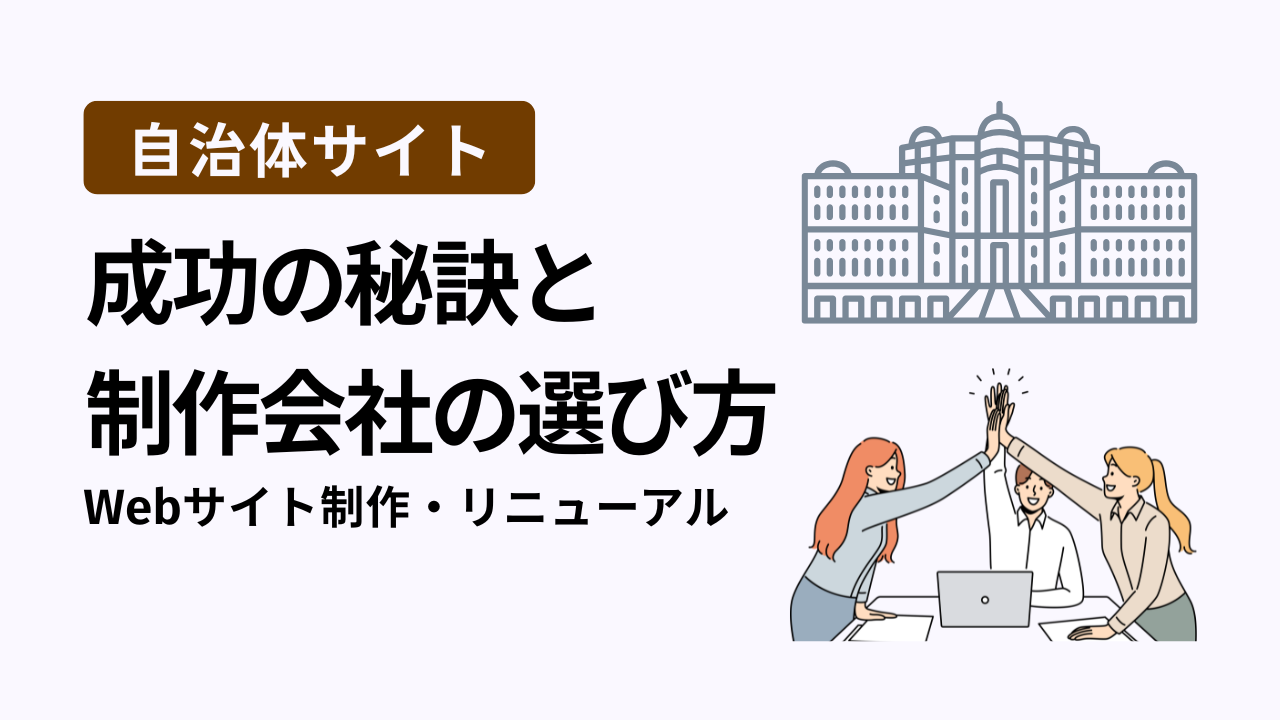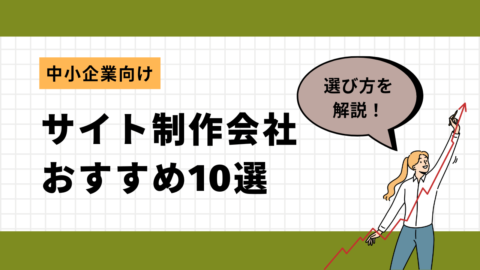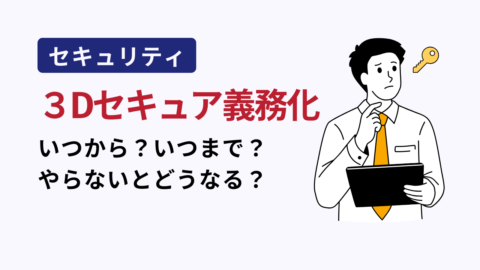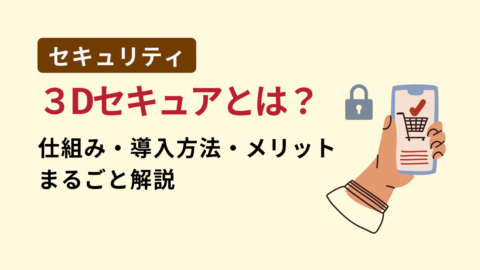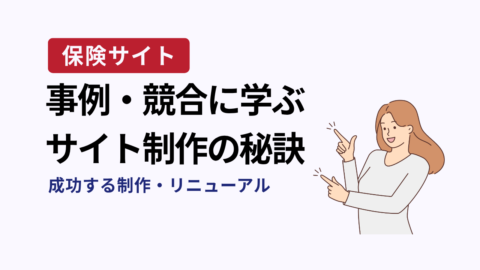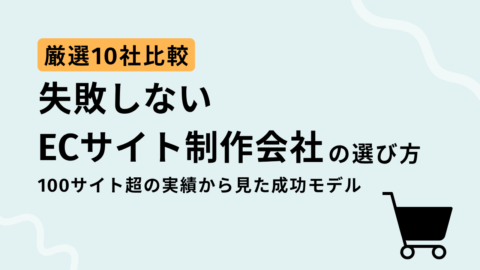近年、各自治体にとって「紙中心・窓口中心」の業務フローを抜本的に見直し、Webサイトを行政サービスの”フロント窓口”へと進化させることが急務となっています。とはいえ、
「どんな機能を備えればDX時代の住民ニーズに応えられるのか」
「アクセシビリティや災害時の緊急更新など公共サイト特有の要件を満たすには、どの制作会社を選べばよいのか」
と悩む担当者も多いはずです。
本記事では「自治体Webサイト制作における課題と解決策」「信頼できる制作パートナーの選定方法」という2つの軸から、自治体がWebサイト制作を強化すべき背景・設計ポイント・パートナー選定基準・成功事例まで、徹底的に解説します。これからリニューアルを検討する自治体の企画担当者やシステム担当者はもちろん、公共案件への参入を目指す制作会社の方にも役立つ内容です。
自治体がWebサイト制作を強化すべき背景
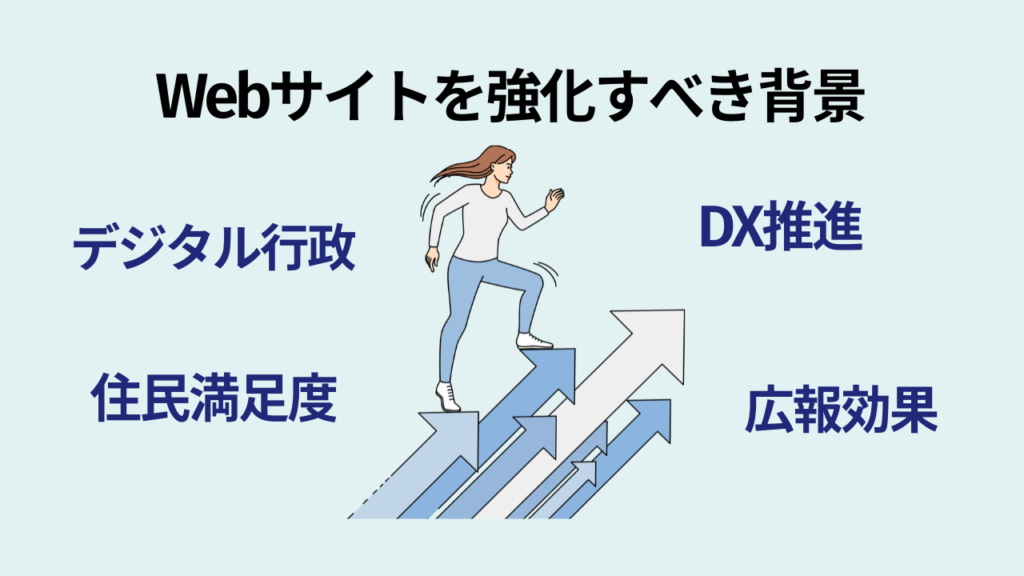
デジタル行政・DX推進の高まり
2021年に創設されたデジタル庁は、総務省と連携し「自治体DX推進計画」を策定しました。
全国1,741の市区町村に対し、①オンライン申請、②電子決裁、③オープンデータ整備など6領域のDX目標を設定しています。
デジタル庁ダッシュボードによれば、2024年7月時点で市区町村の83.1%がDX推進体制を整備済みで、前年の75%から約8ポイント伸長しました。
一方で、「庁内での帳票起票までは電子化したが、住民ポータルは旧CMSのまま」「委託先が分散し保守コストが肥大化」など、“Webサイトだけ置き去り”の自治体も散見されます。
真の意味でのデジタル行政を実現するには、住民との接点となるWebサイトの抜本的なリニューアルが不可欠です。
現代的な自治体Webサイトに求められる要件は以下の3点です。
1. 住民体験を重視したUI/UX設計 ― スマートフォンファースト、直感的なナビゲーション、オンライン申請への導線設計
2. 統合型コンテンツ管理システム ― 各部署が自律的に更新できる権限管理と、全体の統一性を保つデザインシステム
3. クラウドネイティブな基盤構築 ― 災害時でも安定稼働し、アクセス集中にも耐える拡張性のあるインフラ
これらを実装するには、Webアクセシビリティ、情報セキュリティ、インフラ冗長化を同時に考慮できるWeb制作会社が不可欠です。
検索結果に並ぶWeb制作会社の実績を見ると、1,000ページ超の移行とJIS X 8341-3:2016適合AA※をセットで納品しているケースが多数あり、技術的ハードルの高さがうかがえます。
DX加速の最後のピースは、こうした専門性を持つパートナーとの協働と言えるでしょう。
※JIS X 8341-3:2016適合AAとは、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016における、達成基準の適合レベルの一つで、「AA」は、A(最低レベル)よりも高いレベルで、標準的なレベルとされ、公的機関が準拠を推進しているレベルでもあります。(簡単に言うと、高齢者や障害者を含む全ての人がWebサイトを利用できるよう定められた日本の標準規格)
住民満足度向上と広報効果
防災情報、子育て支援、イベント告知など、自治体が発信する情報は生活密着型であるほど「正確性」と「速報性」が求められます。
モバイル社会研究所(2023)によると、自治体公式アプリの「利用意向あり」は約7割、実際のインストール率は70代で25%に達しており、高年齢層でのニーズが顕著です。
しかし「アプリやWebサイトは見るが、サイトが使いにくい」という声も少なくありません。
そこで近年のリニューアルでは、以下のUI/UX強化が進んでいます。
主な改善ポイント
・ レスポンシブ + PWA対応※ ― 端末を問わず”アプリライク”な操作を実現(ホーム画面への追加、オフライン閲覧、プッシュ通知など、ネイティブアプリのような機能と操作感)
・アクセシビリティAA適合 ― 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」が求める水準
・災害モード切り替え ― CMSに”災害テンプレート”を登録し、バナー1クリックで非常時レイアウトへ
※ PWA対応とは、 Progressive Web Apps ウェブサイトをネイティブアプリのように利用できるようにする技術
これらの導入により、電話問い合わせが40~50%減少し、業務効率が向上した自治体関連サイト(防災ポータル・ボランティアセンター等)の報告もあり、Web最適化が職員の工数削減と住民の満足度向上を同時に実現する好例となっています。
自治体のWebサイト制作で押さえるべきポイント
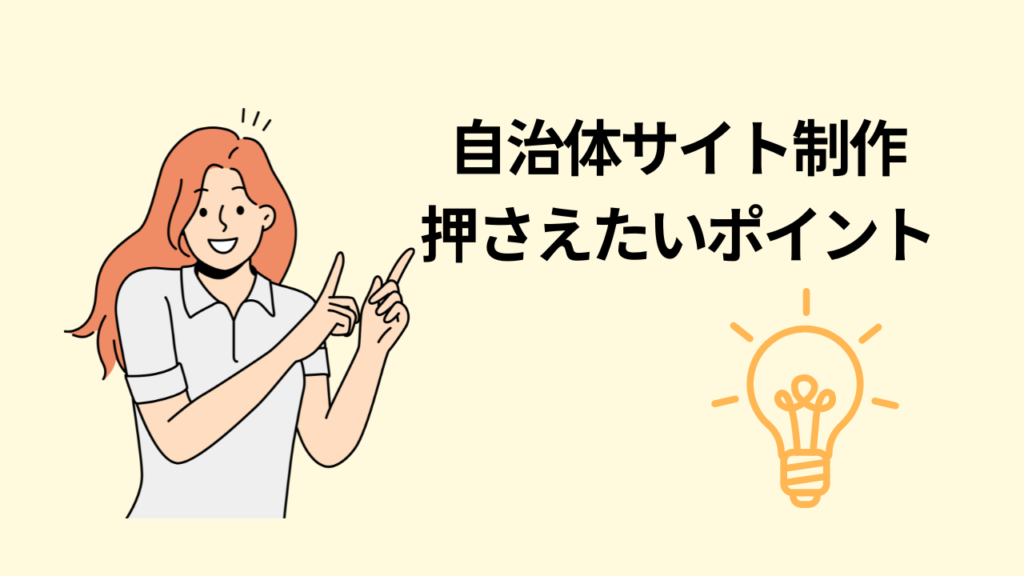
アクセシビリティとユーザビリティの両立
自治体サイトは「住民全員の公共インフラ」です。
高齢者・障がい者・外国籍住民をはじめ、多様な利用者がストレスなく探している情報へ到達できるよう、アクセシビリティとユーザビリティを同時に高い水準で実装することが必須となります。
アクセシビリティ水準の確保
総務省の2023年調査では、全国862自治体サイトの30.5%にJIS X 8341-3:2016(A/AA)不適合箇所が残存していることが判明しました。
これは、視覚・聴覚・運動機能に制約のある利用者が、サイトの一部機能を使えない状態を意味しており、公共サービスへの平等なアクセスを阻害する深刻な問題です。
課題解決に向け、以下のアプローチが推奨されます。
「JISに適合する」ことは最低限満たすべき基準であり、そこからさらに使いやすさや操作性を高めるUX(ユーザー体験)の設計が求められます。
- JIS X 8341-3:2016適合を出発点に、JIS以上のUXを設計
- 文字拡大ボタン・配色コントラスト調整に加え、標準で音声読み上げエンジンを搭載
- カラーのみで情報を伝えないアイコン設計や、キーボード完結操作でスクリーンリーダー(視覚障がい者などが画面内容を音声で読み上げるソフト)利用者をサポート
- 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」が推奨するチェックリストを要件定義書へ明記
ユーザビリティの向上
人口10万人以下の自治体でもスマートフォン閲覧率は70%を超えています。
モバイル・デスクトップで共通テンプレートを運用しつつ、Service Worker※1によるオフラインキャッシュで災害時の閲覧継続性も担保します。
また、WCAG( Web Content Accessibility Guidelines)/JISの達成基準を満たす代替テキストやARIAラベル※2は、Googleが重視する「Helpful Content※3」アップデートとも親和性が高く、必要な情報を検索プラットフォーム上でユーザーに届ける面でも寄与します。
※1 Service Workerとは、WebブラウザとWebサーバーの間で動作するJavaScriptのスクリプト
※2 ARIAラベルとは、ウェブページの要素にアクセシビリティの高いラベルを付与するためのWAI-ARIA属性
※3 Helpful Contentとは、訪問者に満足感を与えているコンテンツを高く評価するもの
情報設計とCMS運用体制の最適化
自治体サイトは「防災」「福祉」「教育」「子育て」「観光」など多岐にわたるカテゴリを抱え、ページ数1,000~5,000規模が標準的とされます。
実際、大規模なWebサイトで使われるCMSベンダーの導入事例では人口1万人規模の自治体で約1,000ページ、20万人規模で5,000ページ前後というモデルケースが提示されています。
こうした大規模構成を「迷わず」「早く」探せる情報設計にするため、Webサイト制作会社と協働して以下を実装するのが鉄則です。下記はその一例です。
自治体Webサイトにおける情報設計の主要施策と効果
| 施策 | 具体的なポイント | 期待される効果・事例 |
|---|---|---|
| グローバルナビゲーション | 3階層以内+メガメニュー化し、主要カテゴリを常時露出 | 初回訪問者の離脱率を低減(ヒューリスティック評価で最も効果が高い導線改善策の一つ) |
| 対象者別導線 | 「妊娠・出産」「高齢者」「事業者」「住民登録・転入」「観光・イベント」などライフシーンで切り替え | 名古屋市ではFAQ検索と組み合わせて電話問い合わせを約20%削減 |
| 全文検索 + タグ絞り込み | 高度な検索機能をCMSに組み込み (住民が使う言葉と行政用語の違いを吸収する検索システムの導入。例えば「子供 手当」で検索した際に「児童手当」「子育て支援金」など関連する制度も自動的に表示。表記揺れや類義語にも対応し、住民が探している情報に確実にたどり着ける仕組み) | サイト内検索成功率(検索後2クリック以内到達)を大幅に向上した自治体事例あり |
| テンプレート自動出力 | 簡易記法による自動ページ生成→ 定型HTML生成/承認フロー自動付与(従来の「Word原稿作成→制作会社でHTML化→確認→修正→再確認→公開」という6ステップを、「職員が直接Markdown記法※で入力→自動でレイアウト適用→承認ボタンで公開」の3ステップに短縮) | 職員1人当たりの更新工数を大幅に削減(最大約50%の削減事例も報告) |
※Markdown記法とは、テキストを構造的に記述する「マークアップ言語」の一つ
特にCMS選定時は、「承認ワークフローとLDAP※連携で課単位の権限管理ができるか」をヒアリングしましょう。
作って終わりではなく、“更新しやすさ=住民サービスのスピード”と置き換えることで、投資対効果が明確になります。
加えてもう一点、CMSの管理権限が何段階まであるか確認することをおすすめします。
中には権限レベルが2段階しかないものもあり、承認ワークフローに関わるため事前に知っておくことが望ましいです。
※LDAPとは、Lightweight Directory Access Protocolの略で、ネットワーク機器やユーザの情報を管理する「ディレクトリサービス」へ接続するためのベンダー中立の標準プロトコルのことです。
大規模CMS導入を伴う制作実績の有無がカギ
大規模CMSの例として、Movable Type Premium/Heart Core/RCMS/Joruri CMS/PowerCMS/NOREN/KANATAなどがあり、自治体案件に強いCMSの共通点は「大規模サイト運用を前提としたモジュール構造と多言語・多テンプレート対応」があることです。
例えばHeart Core導入事例では、1,000ページ超サイトの移行により更新工数を80%削減したケースが公開されています。
またJoruri CMSは47都道府県を含む全国300超の自治体実績を持ち、2025年2月リリース例では徳島県牟岐町・大阪府柏原市などが採用しています。
Webサイト制作会社に必ず確認するチェック項目
1. 1,000ページ以上×30~50テンプレートでの構築実績はあるか
2. JIS適合試験→適合声明発行までワンストップで対応可能か
3. 多言語化・PWA・災害モードなど高度機能の実装事例があるか
4. 大規模CMSベンダーと連携した制作・リニューアル実績があるか
こうした専門要件への対応実績は、各制作会社のWebサイトや事例紹介資料で確認することができます。
自治体案件の豊富な経験を持つ会社では、ホワイトペーパーや詳細な導入事例を通じて、技術力と過去の取り組みを具体的に公開している傾向があります。
自治体特有の運用課題を見据えた設計
自治体では「課ごとの縦割り文化」「担当異動による属人化」「限られたリソース」が慢性的課題です。
制作段階から運用課題を想定し、“誰がやっても迷わず更新できる”サイトに仕立てることが、制作会社と自治体双方の負荷を最小化します。
制作会社に要求すべき運用支援機能
RFP時点で「要求仕様」として書面化し、提案段階で“更新フローのモック演習”を依頼すると具体的な費用対効果を測定しやすくなる機能や設定の例をご紹介します。これらは結果として、保守費用の見積もり精度向上や年度更新時の予算確保のしやすさにも直結するため参考にしてください。
1.緊急時対応を想定したテンプレート設計
災害情報の即時公開機能や、トップページの緊急時切り替え機能の実装を要求しましょう。
平時から緊急時モードへワンクリックで切り替えられる仕組みがあれば、職員の負担を大幅に軽減できます。
2.定型業務に特化した更新機能
議会資料や申請書など、頻繁に更新する定型コンテンツについては、専用の入力画面を用意してもらいましょう。HTMLの知識がなくても、必要項目を入力するだけで自動的にページが生成される仕組みを要求することで、更新作業の効率化が図れます。
3.SNS連携による一括配信機能
Webサイトの更新と同時に、LINE公式アカウントやX(旧Twitter)へ自動投稿される連携機能を仕様に含めるといった工夫もおすすめです。一度の作業で複数の情報発信チャネルをカバーできれば、迅速な情報提供が可能になります。
4.引き継ぎを前提とした研修体制
納品時の研修だけでなく、動画マニュアルやよくある質問集の作成も依頼しましょう。人事異動があっても新任者がすぐに操作を習得できる環境を整えることで、属人化リスクを回避できます。
情報設計・CMS・運用最適化のポイントまとめ
・DX推進は進むも、多くの自治体でWebサイトが置き去り状態 ― 住民との接点であるWebサイトのリニューアルが急務
・大規模CMS × 情報設計 × 運用フローをワンパッケージで提案できる制作会社を選定
・アクセシビリティ(JIS X 8341-3:2016適合)と運用しやすさの両立が、住民サービス向上の決め手
制作会社選定のポイント ― 自治体サイトを任せる際の基準
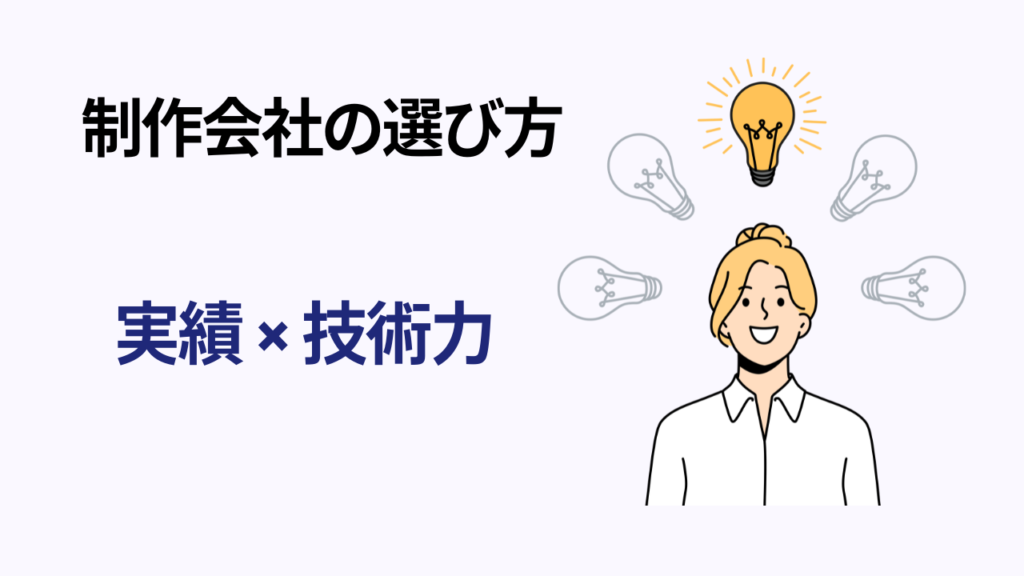
「自治体実績 × 技術力」が第一フィルター
公共調達、とくに情報システム/Webサイト分野では総合評価落札方式(技術点+価格点)が主流になりつつあります。政府の「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」およびデジタル庁調達マニュアルは、価格点と技術点の配分を価格1:技術1を基本とし、案件の難易度に応じて最大で価格1:技術3まで技術点比重を高められると定めています。
したがって技術提案が弱い制作会社は、価格を下げても加点が伸びず落選しやすい構造です。
技術力を測る3つの指標
| 評価軸 | 着眼点 | 最低合格ライン |
|---|---|---|
| 大規模CMS実績 | Heart Core/Joruri/Movable Type Premiumなど、マルチテンプレート+LDAP連携を伴う案件数 | 1,000ページ超×5件以上 |
| JIS X 8341-3適合率 | アクセシビリティ試験→適合声明までを制作会社主導で実施した件数 | AA適合取得3件以上 |
| インフラ/DX連携 | AWS ゾーン跨ぎ冗長化、電子申請API、PWA実装などの開発実績 | 3項目以上を網羅 |
提案書で必ず確認したい3点
1. UI/UXで実績のある専任担当の有無
2. 類似規模自治体の移行スケジュール&KPI ― ページ数・工期・工数削減率など
3. CMSベンダーとの協業体制 ― 直接サポート契約か二次請負か明示
技術評価を高める“証憑”を準備
総合評価では技術点を裏づける証憑(JIS適合声明、ISO 27001、等の提出を求めるケースもある)を添付できるかが勝敗を左右します。ガイドラインも「評価項目ごとに確認資料を提示すること」を推奨しており、提出済みの証憑が多い提案ほど技術点で優位に立てます。
【まとめ】制作会社選定のポイント
・実績:1,000ページ超の自治体案件が5件以上あるか
・証憑:類似案件でUI/UX改善の実績を提示できるか
・協業体制:CMSベンダーと直接契約で長期保守が担保されているか
これらを満たす制作会社は、技術点を最大化しつつ価格競争にも強く、入札を有利に進められます。
運用サポート体制とコスト
①総コストは「初期+運用保守」で評価
自治体サイトの予算検討では、構築費だけでなく公開後に毎年発生する保守費まで含めた「総所有コスト(TCO)」を把握することが欠かせません。ここでは民間サイトとの相場比較を示しつつ、自治体特有の費目がどこで増えるのかを整理します。
【表】自治体Webサイト制作・運用費用の相場比較
| 区分 | 参考データ |
|---|---|
| 民間(企業サイト)Webサイト制作費用 | 平均82.5万円、中央値43.4万円 |
| 自治体リニューアル費用(初期) | 300万~1,500万円 例:富士吉田市 1,502.9万円 |
| 自治体運用保守(年額) | 100万~800万円 例:京都市公式サイト運用保守 785.4万円 |
| 運営代行(民間中央値) | 月額約9.3万円(=年間 約111万円) |
自治体案件ではアクセシビリティ試験や多言語、BCP(Business Continuity Plan事業継続計画)対応が加わるため、民間サイトと比べて初期費・保守費が3~10倍の水準になります。
②コストを押し上げる要因と抑制策
計画段階で見落としやすい追加費用のトリガーを把握しておくと、入札後の増額リスクを抑えられます。ここでは代表的な要因と対処法を対比形式で整理しました。
【表】自治体Webサイトの追加コスト要因と抑制策
| 要因 | コストへの影響 | 抑制ポイント |
|---|---|---|
| 後付け機能(多言語・PWA等) | 見積もりが1.3~1.6倍に膨らむ傾向 | 要件定義で「標準機能」として盛り込む |
| アクセシビリティ再試験 | 年1回以上の試験が必要 | 自動ツール+専門家レビューを保守にセット |
| 人事異動による属人化 | 更新が停滞し、追加委託が発生 | 操作マニュアルと定例レポートを保守範囲に含める |
【まとめ】コスト相場と抑制のコツ
・総所有コストの視点で初期費と保守費を合算し、長期の財政計画に落とし込む
・モデル試算を叩き台にしつつ、自団体のページ数・機能要件でスケール調整
・コスト増の要因を事前に解消し(多言語・PWA・アクセシビリティ再試験・属人化対策)、TCO※を最適化
※TOCとは、Total Cost of Ownershipの略称で、企業がITシステムを導入する際に必要となる、ソフト・ハードの購入や維持管理にかかわるすべての費用の総額を指します。
自治体Webサイト制作の主な流れ
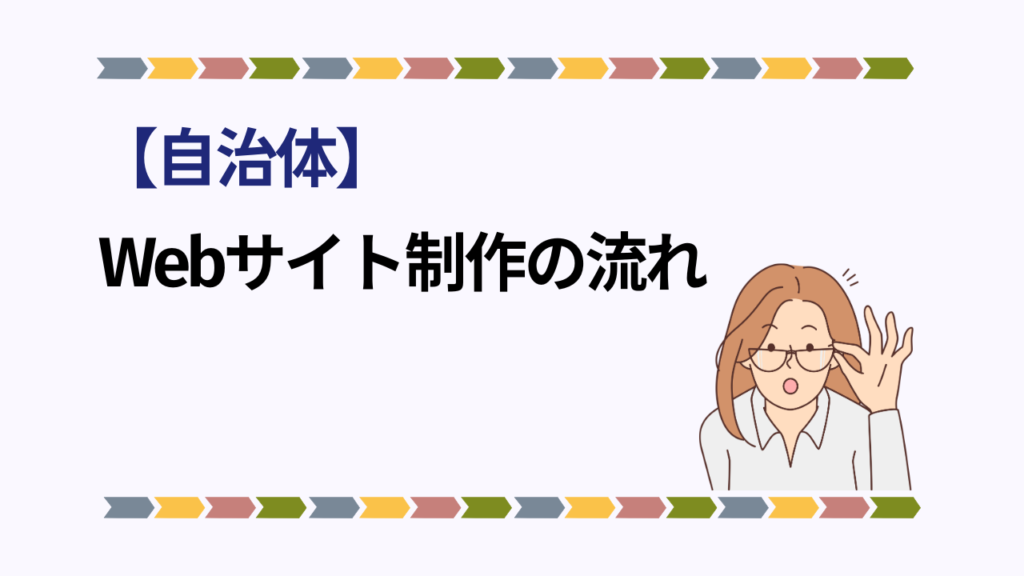
要件定義・ヒアリング:”行政DX”とサイト目的を同期
プロジェクトの成否は、最初の要件定義フェーズで住民体験(UX)と行政DX目標をどこまで具体化できるかにかかります。総務省「自治体DX推進計画」でも、オンライン手続き化の対象範囲と住民利便の両立を要件定義書に明示することが推奨されています。
【表】要件定義・ヒアリング段階で準備すべき主要タスクと成果物
| ステップ | 主要タスク | 成果物 |
|---|---|---|
| ステークホルダー調整 | 首長、情報政策課、各所管課、広報課、住民代表(場合によっては議員)を巻き込み「誰が何を決定するか」を整理 | プロジェクト体制図・RACI図※1 |
| 現行サイト診断 | GA4/Page Speed/アクセシビリティ自動診断で課題を可視化。必要に応じて5人前後被験者テスト・ヒューリスティック調査を実施 | ・ヒューリスティックレポート (客観的評価をするため外部委託を推奨) ・現状分析レポート ・被験者テスト分析レポート |
| 住民ニーズ・業務要件収集 | 行政手続き一覧、窓口業務フロー、紙申請書類を棚卸しし「オンライン可否」を判定 | 要件定義書(機能・非機能) |
| コンテンツインベントリ※2 | ページ、PDF、画像、オープンデータを一括CSV化し、移行可否と責任課をマッピング | コンテンツ移行台帳 |
| RFP/プロポーザル準備 | 上記資料を基に調達要件(JIS AA・PWA・API連携・冗長化など)を明示 | 調達仕様書・評価基準表 |
※1 RACI図とはプロジェクト内すべてのタスク、マイルストーン、成果物における役割と責任をメンバーに振り分けた表のこと。
※2 コンテンツイベントリとは、デジタル製品や Webサイト内のコンテンツ資産をすべて包括的かつ構造的に集めたものであり、コンテンツの位置、形式、メタデータ、主要な属性)など各コンテンツに関する詳細な情報をまとめた目録を指します。
Webサイト制作期間の目安
総務省「情報システム調達モデル」や複数自治体の実施要領を見ると、ヒアリング開始からRFP公開まで約2~3か月(≒60~90日)が標準レンジです。奥州市の公共施設予約システムRFP(2023年)では、要件定義完了後約70日で公告 → 説明会 → 提案締め切りのスケジュールが組まれています。
成功に向けたポイント
- 非機能要件(アクセシビリティ・セキュリティ・BCP)を要件定義書に明文化
早期に示すほど見積もり精度と工期確度が向上し、後工程の追加コストを防げます。 - コンテンツ移行台帳を先行作成
ページ数・ファイル量・責任課が定量化され、移行コストと所要日数を”見える化”できます。 - 評価基準表を同時公開
プロポーザルの公平性が担保され、制作会社側も要件を逆算しやすくなるため、質の高い提案が集まりやすい。 - 受け渡しとコミュニケーションルールの明確化
CMSベンダーとWeb制作会社の役割範囲と受け渡し方法、コミュニケーション手段とルールをあらかじめ決めておくとプロジェクトを円滑に進行することができます。
制作工程の詳細と実施ポイント
要件定義が完了し、制作会社が決定したら、実際の制作工程に入ります。以下、各工程で押さえるべきポイントと、自治体が制作会社に確認すべき事項を解説します。
- 工程1:現状課題分析・ペルソナ設計
-
現状課題分析は客観性が重要なため、社内で行わず、外部の専門コンサルタントに委託することを推奨します。抽出された課題を踏まえ、Webサイトの想定ターゲットをペルソナ設計に反映し、プロジェクトに携わるメンバーが共通認識を持つことが大切です。
- 工程2:サイトストラクチャ
-
ウェブサイトの情報構成やページ間の関係性を指します。具体的には、サイト内のコンテンツをどのように整理し、ユーザーが目的の情報にたどり着きやすくするか、という設計のことです。SEO(検索エンジン最適化)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の向上にも影響するため、サイト構築において重要な要素です。
- 工程3:サイトマップ
-
ウェブサイトのページ構成を地図のように一覧で示したものです。ユーザーと検索エンジンがサイトの構造を理解しやすくするために作成されます。ユーザー向けのHTMLサイトマップと、検索エンジン向けのXMLサイトマップの2種類があります。
- 工程4:情報設計・ワイヤーフレーム
-
住民が必要な情報に迷わずたどり着けるよう、メガメニュー、対象者別導線、タグ検索UIなどの設計を行います。制作会社にはFigmaなどのツールでプロトタイプを作成してもらい、実際の操作感を事前に確認することが重要です。
- 工程5:ビジュアルデザイン
-
自治体のブランドイメージを保ちつつ、視認性の高いデザインを実現します。色・書体・コンポーネントをデザインシステムとして体系化し、今後の更新でも統一感を保てる仕組みを構築してもらいましょう。
- 工程6:CMS基盤構築
-
Heart Core、Movable Type Premium、Joruri CMSなど大規模サイトに対応したCMSを選定・構築します。LDAP認証による職員アカウント管理、承認ワークフロー、外部システムとのAPI連携などは、この段階で実装を完了させることが肝心です。
- 工程7:テンプレート実装・アクセシビリティ試験
-
デザインをCMSテンプレートに落とし込み、JIS X 8341-3:2016適合試験を実施します。自動チェックツールと専門家による手動チェックの二段階で検証し、確実な適合を目指します。
- 工程8:コンテンツ移行
-
既存サイトの大量コンテンツを新サイトへ移行します。Markdown、CSV、APIなど複数の手法を組み合わせることで効率化が可能です。品質確保のため、多くの自治体では「担当課による内容確認→制作会社による修正→職員の最終確認」という3段階のチェック体制を採用しています。この手法により、移行ミスを最小限に抑えながら、効率的な作業進行が実現できます。
- 参考:開発期間の目安
-
公開されているRFP・事例を見ると、ページ数1,000~5,000/テンプレート数30~100規模で6~9か月が標準レンジ。要件外機能(多言語・PWAなど)を後付けすると、ベンダー見積もりが1.3~1.6倍に跳ね上がるケースがあると報告されています(CMSベンダーヒアリング結果)。
- 確認推奨:CMS 選定時の要点
-
・テンプレート自動生成機能(Markdown → HTMLなど)が標準か
・多言語・PWAプラグインを追加開発せず導入できるか
・JIS AA適合試験支援やデータ移行ツールが公式で用意されているか
これらを満たすCMSを選ぶと、並行開発による工期短縮と移行コストの抑制が期待できます。
テスト・公開・運用 ~公開後30日が勝負所
以下は公開前後の重要なポイントを挙げています。抜け漏れのないようチェックしてください。
- 総合テスト
機能/結合:フォーム送信、API連携、検索、災害モード切り替え
アクセシビリティ再試験:公開URLでJIS適合を再チェック
負荷:ピークPV×3倍でJMeterを実行し、冗長構成を検証 - 公開手順
DNS/SSL切り替え:可能であれば深夜帯に実施し、旧サイトはサブドメインで一時待避
301リダイレクト:移行台帳のURLマッピングをCMSに一括登録
監視設定:外形監視アラートを制作会社と職員双方へ通知 - 公開後30日で必ず行うアクション
・404ログをCMSへ取り込み、即日リダイレクトを追加
・GA4探索レポートで検索語句 × 離脱ページを抽出しナビゲーションを修正
・職員・住民アンケートをフォームで収集し次回改善計画に反映 - 運用フェーズ
デジタル庁はアクセシビリティ試験結果を少なくとも年1回公開することを推奨しており、多くの自治体が”適合維持”を毎年度宣言しています。また、月次アクセスレポート+改善提案を制作会社が提出する運用形態が増えています。
【表】運用 KPI サンプル
| 指標 | 目標値(参考例) | 計測方法・ツール |
|---|---|---|
| サイト内検索成功率※1 | ≥ 80% | GA4(旧Google Analytics) |
| モバイル直帰率※2 | ▲15% | GA4(旧Google Analytics) |
| ページ公開までの平均工数 | 2営業日以内 | CMAのログデータ |
| アクセシビリティ不適合数 | 0件 | 手動および自動試験 |
※1 サイト内検索成功率の定義と前提
「サイト内検索を実行したセッション」のうち、検索結果から一般的な測定目安として2クリック以内または2分以内に目的ページ(制度詳細・申請ページ・FAQ詳細など)へ到達した割合を指します。
「検索を使った人の比率80%」ではなく、検索を使った人の中で目的到達できた割合です。
ここでの想定サイトは行政情報ポータル型(手続きや制度情報の検索が多い構成)の相場としています。
80%という数値は一般的な目安であり、必ずしも全自治体に共通する基準ではありません。
※2 モバイル直帰率の定義と前提
「▲15%」は「基準期からの相対改善(15%減少)」を意味し、「15%以下に抑える」という絶対値目標ではありません。例:基準期の直帰率が60% → 改善後51%を目指す等
サイト特性により差が大きく、手続き型・ポータル型サイトでは改善余地が大きい一方、ニュース・広報中心サイトでは直帰率が高くなる傾向があります。
一般的な改善目標の目安として10~15%程度の低下を掲げるケースが多く、スクロール深度や滞在時間など他指標と併用して評価するのが望ましいとされています。
制作会社を活用するメリットと注意点
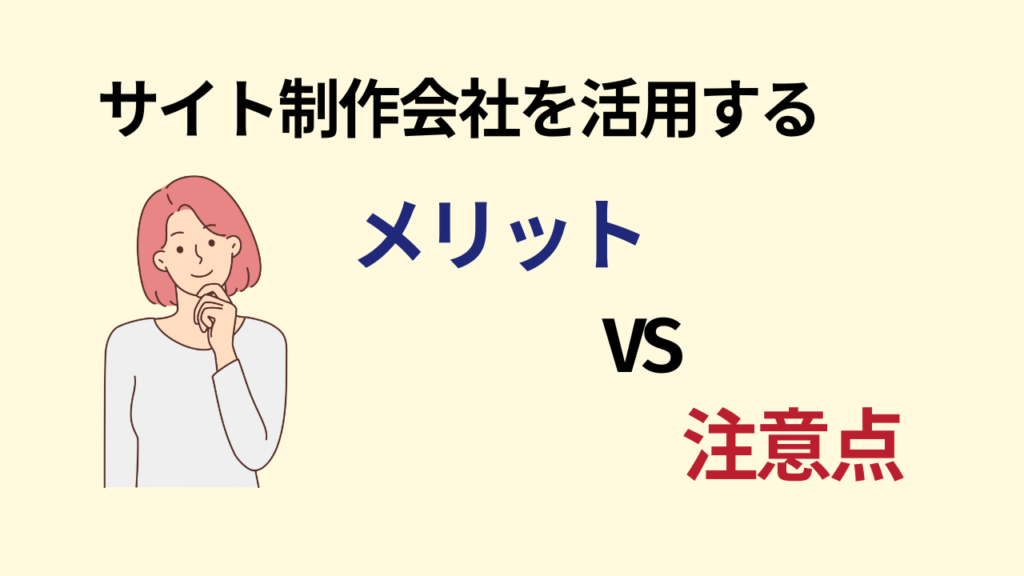
メリット:専門知識・最新技術の活用
自治体サイトはアクセシビリティ、セキュリティ、冗長化、多言語対応など民間サイトより厳格な要件が課せられます。専門制作会社に委託する最大の利点は、こうした公共案件特有の要求を「ワンストップ」で満たせる点です。
【表】制作会社の主要技術領域と期待効果
| 技術領域 | 制作会社が提供する代表的ソリューション | 公開ベースでの期待効果(イメージ) |
|---|---|---|
| アクセシビリティ | JIS X 8341-3:2016 AA適合テンプレート/試験・適合声明 | 試験~声明発行までを一括受託する事例が増加 |
| CMS/UI/UX | Movable Type Premium/RCMSなどの大規模CMS連携 | ページ数1,000超で更新工数を80%削減 |
| インフラ冗長化 | AWS AZ跨ぎ※+自動フェイルオーバー構成 | 災害時ダウンタイムを最小化(各自治体のDR計画で推奨) |
| 多言語対応 | 内蔵翻訳API × 多言語テンプレート | 外国籍住民への情報発信を迅速化 |
| DX連携 | 電子申請/基幹DBとのAPI接続 | 窓口業務をオンライン完結へ |
※AWSのAZ跨ぎとは、複数のアベイラビリティーゾーン (AZ)(Availability Zone)にまたがってAWSリソースを配置し、システムを構成することを指します。これにより、単一のAZで障害が発生した場合でも、他のAZで稼働しているリソースが引き続きサービスを提供できるため、可用性を高めることができます。
IT-Trend(2024)の自治体向けCMS調査では、導入メリットの上位に「迅速な情報発信」と「ウェブアクセシビリティ対応の容易さ」が挙げられ、制作会社経由の導入例が増加しています。

注意点:発注範囲の明確化と公平性のある選定プロセス
注意点①:発注範囲と責任分担の明確化
ティング事業者」という多層構造が標準です。契約範囲が曖昧なまま進めると、リリース直前に「リダイレクト設定は誰の担当?」といった”宙に浮くタスク”が発生し、滋賀県サイト炎上事件(2019年3月にリニューアル後、リダイレクト設定不備により大量の404エラーが発生し、リンク書き換えを県職員が手作業で行う事態となった事例)のようなトラブルに直結します。
【表】自治体Webサイト制作における役割分担例
| 項目 | 想定担当者 | 主な責任 |
|---|---|---|
| CMS基盤構築 | CMSベンダー | 環境構築・API仕様書・保守 |
| 情報設計/デザイン | デザイン会社 | トーン&マナー、テンプレート設計 |
| 実装・移行 | Web制作会社 | テンプレート組み込み、ページ制作 |
| サーバー運用 | インフラ事業者 | SSL、バックアップ、冗長化 |
契約書・要件定義書には「誰が・何を・どこまで」を示すスコープドキュメントを必ず添付し、変更管理プロセスを合わせて規定しましょう。
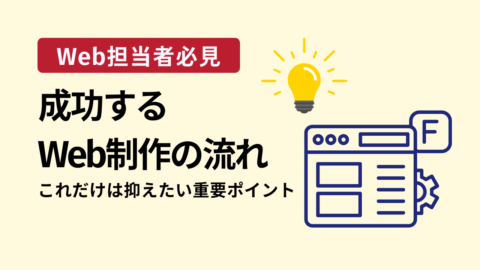
注意点②:公平性と透明性を担保する選定プロセス
流ですが、評価基準が不透明だと議会質問や外部監査の対象になります。デジタルマーケティング・アドテクノロジー分野の上場企業であるMicroAd社の解説記事でも「技術提案書に対する明確な評価基準と選定委員を示すことが重要」と明記されています。
そこで次の3点を仕様書段階で開示する自治体が増えています。
- 評価シートの公開 ― 加点・減点理由を含めた評価基準表を募集要項と同時公開
- 選定委員の役職・専門領域を公表 ― 個人名は伏せても、構成の客観性を示す
- ユーザビリティテスト/プロトタイプ提出の評価項目化 ― UI/UXの実証を事前に行い、提案の実効性を判定
このプロセスを透明化すると、参加企業側も納得感を持って提案でき、結果として質の高いWeb制作会社が集まりやすくなると期待されます。
注意点③:情報共有・承認プロセスを設計段階で固める
テックタッチ社が2025年6月に発表した自治体DX調査では、自治体職員の48.6%が「人事異動でノウハウが切れる」と回答しています。制作会社と職員の連携を途切れさせないためには、プロジェクト初期に以下を明文化することが欠かせません。
・窓口の一本化 ― ICT推進課や広報課などに専用チャネルを設置
・更新・承認フロー図を共有 ― 例:各課長 → 情報政策室 → 制作会社の順で承認
・CMS操作マニュアル/動画教材を納品スコープに含める
・定例会&QA窓口 ― 毎月の保守報告に加え、緊急時ホットラインを設定
これらの運用ドキュメントを制作会社側で定型化しておけば、年度ごとの担当者交代でもリセットリスクを抑制し、長期的かつ安定的なWebサイト品質を担保できます。
【まとめ】制作会社活用ポイント
・制作会社活用の核心は「公共特有の技術要件をワンストップで満たす」こと
・スコープと責任分担を文書で可視化しないと、リニューアル時に炎上リスクが高い
・公平・透明なプロポーザルと異動に強い情報共有体制がプロジェクト成功の鍵
本記事のまとめ
自治体Webサイト制作は「公共インフラをつくる仕事」―アクセシビリティ、セキュリティ、BCP、DX連携を同時に満たす高度な専門性が要求されます。
制作パートナー選びのカギは、以下3点
・大規模CMS × アクセシビリティ適合の実績
・JIS試験~災害モードまでワンストップで対応できる体制
・コスト内訳の透明性と運用自走支援
発注側(自治体)は要件定義段階で非機能要件を明文化し、スコープと責任分担をドキュメント化することで、トラブルリスクを大幅に削減できます。
最終終チェックリスト
・JIS X 8341-3:2016適合AAを前提にしているか
・CMSの承認フロー・LDAP連携が要件に含まれているか
・災害時バナー/PWAオフライン対応を盛り込んだか
・発注書にスコープ・SLA・ガバナンス要件を明示したか
自治体サイトは一度公開して終わりではなく、住民ニーズ・法改正・技術進化に合わせた継続改善が求められます。専門性の高い制作会社と協働し、数字で成果を測りながらPDCAを回す―それが「行政DX時代」にふさわしいWebサイト運営の秘訣です。